平成最後の冬休みが終わりました。
冬休みといえば、、 そう自由研究!(もしかして北海道だけ?)
そうですまた大人の本気を見せる機会がやってきました。
2018年の夏休みは自由研究でこんなものを作っています。
小学生の次女と協力して、「2019年冬休みの自由研究」という困難なプロジェクトを完遂させることができました。
その偉大な足跡をここに残します。
Pendulum Wave(ペンデュラムウェーブ)を作ることに
去年の12月の上旬だったと思います、次女が冬休みの自由研究どうしようといってきたので、とりあえず自分で考えてみるように言いました。
後日次女が出した答えは
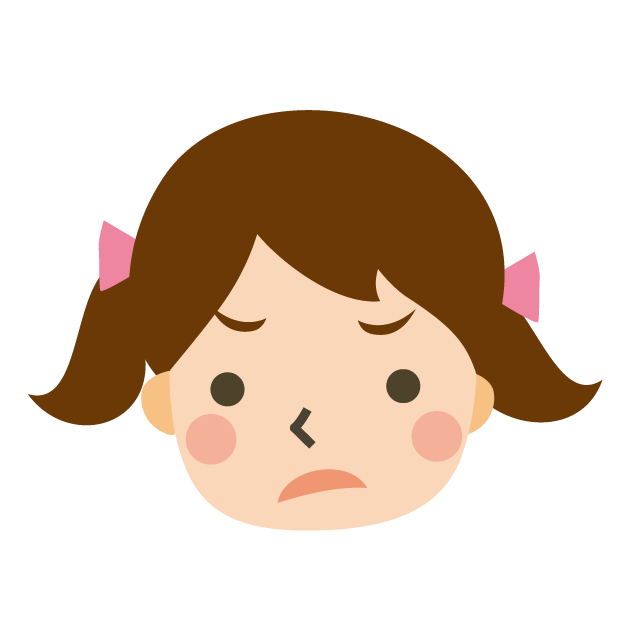
戦車作りたい

ん~ どうでしょう? 戦車って!?
次女がネットで探した戦車は、木の球体を車輪にし、ダンボールの内側のボコボコした部分をキャタピラーにした簡単なものでした。
自走できない、砲台から弾も出ないような戦車は認めんぞ!キリッ!
次女は「あっそう」という関心のない表情で、「じゃ パパ考えて」と、、、
ああ 言われなくても考えるぜ!
いろいろ探した結果これを作ることにしました。
Pendulum Wave (ペンデュラムウェーブ)
YouTube:Grand illusions
振り子のひもの長さを変えて、周期をずらし動きの変化を楽しむものです。
上手くできればヘビのような動きから、一定のパターンの動き、またヘビのような動きと同じ動作を繰り返します。
これを作ってみます。レッツ チャレンジ!
ペンデュラムウェーブの材料紹介
とりあえずYouTubeにある動画をみて構想を練り、材料を買ってきました。

まず振り子の球として釣りに使う丸い重りと、糸としてテグスを用意。
振り子を支える土台として



塩ビパイプをつなぐときに使うもの。複数個。

その塩ビ管に入るくらいの太さの木材数個。

木ねじも購入。
他に夏休みの自由研究で使ったPPシートが余っていたので、それも使用しました。
材料費は2000円くらいかかっているかも、、、
ペンデュラムウェーブを作る
本格的に作る前に球の部分をいろいろ試してみました。
球の部分は釣りの重りなので、真ん中にテグスを通す穴が貫通しています。
試作1号
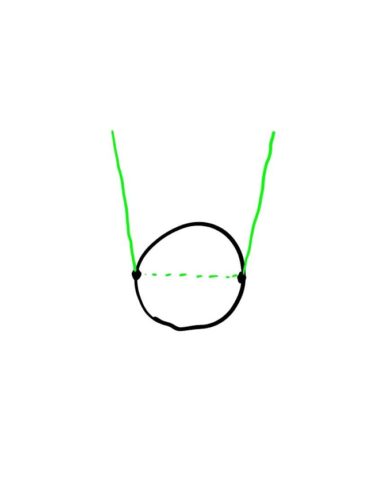
緑色の線はテグスです。
真ん中の穴にテグスを通して、2点で支えて動かしてみました。
テグスの細さに対して、重りの穴が大きいようで、揺れている間お互い干渉してしまいます。
結果、振り子の動作が長続きしないので、これは却下に。
試作2号
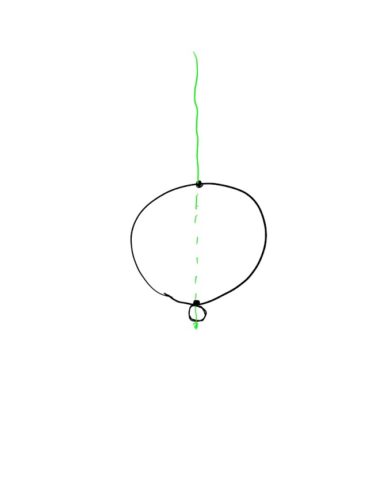
今度はビーズにテグスを結んで、重りの穴を通し、1点で支えるような形にしてみました。
3個くらい作って動かしてみると、1点で支えた場合、左右にふらつき隣にからまって安定しません。
よってこれもダメ。
なんだか自由研究らしくなってきた。
試作3号(これを採用)
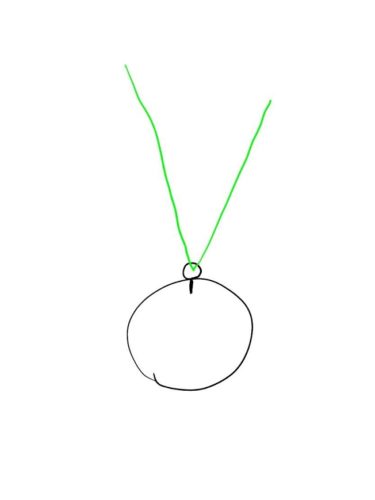
2点で支えるのは重要であると考え、重りの穴にヒートンを強力ボンドでつけて、ヒートンの輪の中にテグスを通すようにしました。
ヒートンとはこのような形をしたものです。
使った接着剤はこちら 超強力です。

こんな感じです。これを10個作ります。
土台部分を作成
ここはサクサク材料を切ってつなげるだけです。
本当は塩ビパイプで作りたかったけれど、パイプカッターが高かったのでやめました。普段使うこともないので。


はめてみるとキツキツだったので、接合部分は木材にヤスリをかけて削りました。
これを2個作ります。
振り子の部分を作って土台とあわせる
理想としては微調整できるような装置、たとえばギターの弦をしめるときのやつみたいのを使いたかったけれど、予算の都合で無理かなぁと、、、
いろいろ考えた結果
文明の利器 セロテープ を使うことにしました。
PPシートにセロテープで貼り付けて行きます。
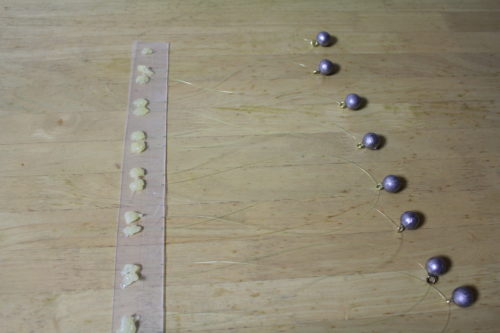
写真ではグルーガンで補強していますが、メンテナンスがしづらくなるので、最後はセロテープのみに落ち着きました。

これを木ねじで角材に留めて、土台の真ん中の部分にはめ込んで完成です。

まとめ・反省
ここまで完成して動かしてみたところ、どうも上手く同期しないので調べてみると衝撃的な事実が!
ひもの長さは決まった比があるようです、、、
私は単に5ミリくらいづつ短くしただけ やっちまった。
まあそれも100分の1ミリ単位だから、最後は人の手で調整しないとダメなようですね。
反省点として
BGMは「甘茶の音楽工房」さんです。
今回は私の意見を押し切って失敗してしまったから、次回夏休みの自由研究は次女の意見を尊重しようと思っています。
ちなみに夏休みは何を作りたいんだい?
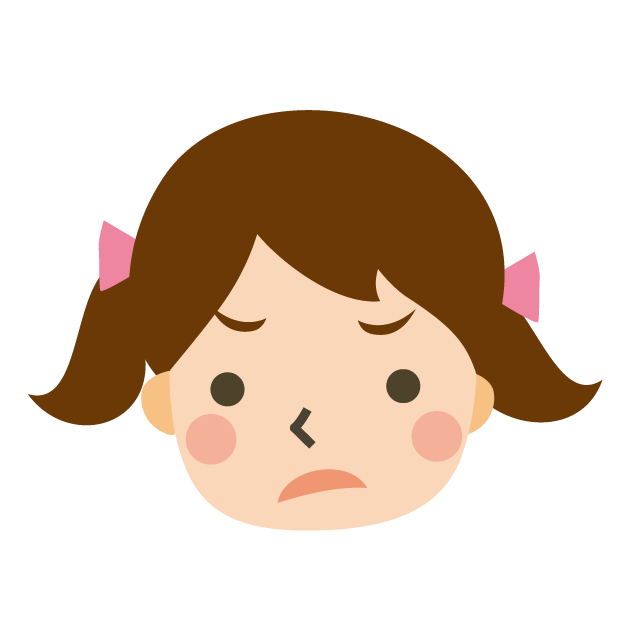
太鼓のバチ

おっ、、 OK牧場!


































コメント